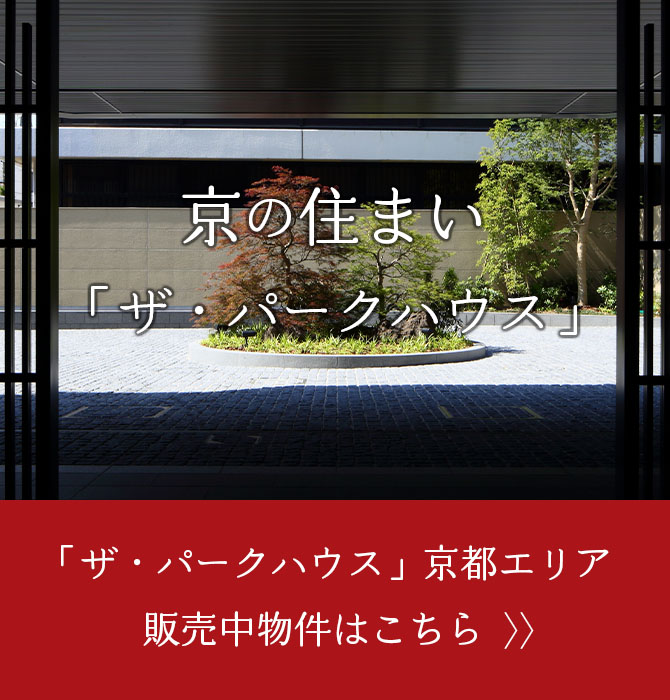2024.09.13
#うるしのいっぽ#持続可能なモノづくり
#漆器を日常に
#漆器を日常に
次世代に継いでいくため、
漆の価値を新しく創造する
茶の湯と共に発展した京漆器や、
建築物や調度品などの塗装に用いられ、
京都の様々な伝統・文化と
深いつながりを持つ、天然素材・漆。
実は1万年以上前からずっと人類の暮らしの
そばにあり、重宝されてきた素材です。
使い捨てとは真逆、使い続けることで
生まれるキズもまた漆アイテムの
付加価値となります。
今回は漆の精製を生業とし、
環境に配慮した取り組みにも
力を入れている、
堤淺吉漆店四代目の堤卓也さんに
お話を伺いました。

「Und.」には様々な種類の漆が店頭に並ぶ

店舗の裏にある作業所
職人のこだわりに応じる
漆のプロフェッショナル
地元で愛される佛光寺のほど近く、細い通りに佇む堤淺吉漆店。2024年春、同店のフラッグシップショップ「Und.(アンド)」をオープンしました。漆芸の道具、金継ぎ・拭き漆の体験キットなどが並び、漆に興味のある方、工芸を学ぶ学生、職人さんなど、誰もが気軽に訪れることができる空間となっています。1909年(明治42年)創業からこの地で商売を続けてきた堤淺吉漆店は、木から漆を採取する「漆掻き職人」と木地に漆を塗る「塗り師」、その両者をつなぐ漆の製造・販売業を営んでいます。ツヤ、乾き具合、粘度を調整して塗り師の方々の要望にフィットする漆に仕上げていく、職人のこだわりを支える仕事です。堤淺吉漆店で精製・販売した国産漆は、国宝・重要文化財や世界遺産建造物の修復、京都迎賓館調度品などにも採用されています。国産漆取扱量、国内トップシェアと聞けば安泰に聞こえてしまうけれど、実際はそうではありません。
「戦後、ライフスタイルの変化や化学塗料の進化に伴い、国産の漆産業は衰退。現在は国内で使用する漆の大半を海外産に頼っています。その海外産ですら、昨今は日本と同じく後継者不足や漆の木の減少も相まって生産量が減少傾向にあります。もし情勢が変わり輸入が止まってしまったら、漆の文化はたちまち消えてしまいます」

BEYOND TRADITIONで新たな価値観を
吹き込んだサーフボードと自転車

たくさんの工程を経て精製した漆
「植える」ことから考える
持続可能なモノづくり
漆の現状に危機感を感じた堤さんは、できることを考え抜いた末、動き出します。漆の魅力を伝える活動『うるしのいっぽ』、漆の新しい価値観を生み出すプロジェクト『BEYOND TRADITION』、「植える」ことから始めて、採取したらまた植えるという、循環型モノづくりにつなげる『工藝の森』など、次々とプロジェクトをスタートし、活動の輪がどんどん広がっています。
「縄文時代からずっと、漆は人の生活のそばにありました。防水、防サビ、接着できるという特長を持ち、食器に用いても安全な素材です。ただ15年ほどかけて育てた1本の成木から漆が採取できるのはわずか牛乳瓶1本分(約200ml)ほどです。
初めて漆掻きの現場に行った時、苗木から成木になる15年はすごく遠くに思えました。でも現場の林業家の方々とお話すると、50年や100年スパンで物事を考えていらっしゃる。林業家の方が循環を目にできるのは一生に一回と考えると、15年という時間は苗木を植え、漆を採取伐採、再び植えるという循環が自分の生きているうちに何回か見られるかもしれない。そう思えたことで自分も循環の輪の中で役に立てるのでは、と思えるようになりました」

持ちやすく、口当たりの良い漆器を
ぜひ日常に取り入れて

四代目 堤卓也さん
漆や工芸を入口にして
次世代が集うスタジオ
漆を通していろんな人たちと出会い、そこでの気づきを行動につなげてきた堤さん。「Und.(アンド)」という新しい拠点から今発信したいと思っているのは、漆器を日常に戻すこと。「漆の器は熱が伝わりにくいので小さな子でも持ちやすく、手や口に触れた時の感触が柔らか。塗りが剥がれたり、割れたりしたら、漆でリペアすることでモノを大切にする心も育みます。蒔絵や金箔を施した高級な漆器とはまた別ジャンルと認識してもらい、ついたキズまで愛せるような日常の漆器を“面白いやん”と思ってくれる人を増やしていきたいです」「Und.」の3階は、独り立ちを夢見る若手塗り師たちのアトリエや、衣食住と漆を繋ぐワークショプを行うスタジオとして活用しています。1階のショップでは、環境問題への関心から漆の世界に飛び込んできたスタッフが働いています。「学んできたジャンルも関係なく、漆という素材に興味を持ってくれる若い人が増えることがすごく嬉しくて。「Und.」を訪れ、持続可能な自分らしい暮らしを見つけてもらえれば」と、微笑む堤さん。伝統と革新の両輪を回しながら進み続ける姿勢そのものが、京都に根付く文化なのかもしれません。
京都の漆文化を守っていきたい
僕にとっての一生もんは、使うほどにかっこよくなるもの。革とかデニムって使うほどに味わいが出てかっこよくなりますよね。漆の塗装を施した器も、家具も、サーフボードも、ずっとリペアしながら、子供や孫の代まで、その経年変化も楽しみながらずっと使い続ける、そんな世界になっていけばいいな、と思っています。
人工的に大量生産されたモノに溢れる社会において、漆は人と自然をつないでくれる、自然の大切さを教えてくれる素材でもあります。京都の代表的な文化である染色、和食、茶道、庭園など京都の文化もまた、自然の恵みと共に発展してきました。京都から離れて暮らしたことで、より一層その自然と共に発展してきた京都の良さが身に染みるようになりました。自分たちが循環の輪の中にいることを忘れず、使い続けることができる漆文化をこの京都という土地で守っていきたいと思っています。
堤淺吉漆店 四代目 堤 卓也

堤淺吉漆店
(つつみあさきちうるしてん)
(つつみあさきちうるしてん)
- 所在地
- / 京都市下京区間之町通松原上ル
稲荷町540 - 交通
- / 京都地下鉄烏丸線四条駅より徒歩6分

※記載の写真、内容は取材当時(2024年7月)のものです。