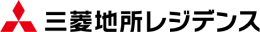一生ものの住まい建築家 前田紀貞が見た、
「ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵」の引力。
2015年09月15日
住む場所を作ることは、その場の空気を作ること——
そんな思いを胸に数々の住空間を手掛けてきた前田さんと、完成したばかりの〈ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵〉を訪ねた。この建物が醸し出す空気は、前田さんをどのように包んだのだろうか。
"一生もの"と言える証。

春には桜が咲き乱れる千鳥ヶ淵の景色を一望にする立地。アクセスのよい都心にして、広大な緑を享受できる住環境だ。
東京都千代田区三番町。
そこは都心にいながらにして自然の豊かな恵みを受ける場所だ。
このエリアの一角、皇居を巡るお堀とその周囲の緑とが千鳥ヶ淵へと緩やかにカーブしていく角地に、〈ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵〉は建つ。
14階建ての各層からすっと伸びる庇、どっしりとした重みを感じさせる御影石の外壁。
もう長くここにあったかのように、その建物は風景に調和して佇む。
皇居はもちろんのこと、官公庁やさまざまな文化施設にもほど近く、いながらにして自ずと〝日本〟やその歴史、そして美意識が感じられる立地。
建物のデザインには、ここに住むことの意味を熟慮した軌跡が反映されている。

敷地の目の前にある千鳥ヶ淵は日本屈指の桜の名所。春はもちろん、夏には青々と生い茂り、冬に見つける新芽もまた楽しい、季節の使者だ。
まず建物の配置。
建物は、敷地の形に対して斜めに振ったような不定形な形をしているのだが、これは周囲への配慮を積み上げて決定されたもの。
皇居の緑を堪能する南東側へ向けて各住戸を開きつつも、敷地のすぐ横にある千鳥ヶ淵戦没者墓苑を見下ろすことのないように軸線をずらす。
さらに敷地の内堀通りに面する側では、街の景色との調和を図るため、ほかの建物と外形のラインをそろえているのだ。
土地への敬意、周囲との協調。
それはとりもなおさず、日本ならではの美意識といえるだろう。

全住戸のリビングが皇居の森側へと開けた作り。幅2メートル近い広々としたバルコニーは、日本らしい軒庇をモチーフにしている。
建物を中へと入っても、その感覚は続いていく。
エントランス、少し幅の狭くなったコリドー(廊下)部分、その先のレセプションと細かに分節化された空間構成は、奥へ奥へと導きながら人々の心を落ち着けていく。
さらに圧巻なのが、そうしてたどり着くロビーラウンジ。
一面の大きなガラス窓の向こうに、敷地の高低差を利用して石を積み上げ、たっぷりとした水の流れる中庭が待っているのだ。
水音と中庭に注ぐ光に、心がふわりと和らぐのがわかる。
パブリックな空気をいきなり遮断してプライベートな空間へと入るのではなく、その中間の領域が設けられるのは、古くから続く日本建築の伝統でもある。

ロビーから見える水の流れる中庭は、作庭家・大北望氏の手によるもの。選り抜かれた石や木々が作り出す“自然”が心を穏やかに鎮めてくれる。
とはいいつつも、いたずらに〝和〟を主張しているのではない――
それは、スペースの随所に国内外の気鋭アーティストによるアートピースも置かれるこの共用部はもちろん、住戸内部のインテリアからも明らかなこと。
重厚感のある天然石や木など本物の素材をたっぷりと用いつつも、無駄な装飾のない、潔いラインで描かれた各住戸のデザインは、ごくモダンなセンスによるもの。
全住戸のリビングは皇居の森に面しており、季節や時間の移ろいを愛でながら、この住まいでの時間は過ぎていく。

エントランスとロビーをつなぐコリドー(廊下)部分。上質の素材を使ったシックな空間が、分節されながらつながっていく。
単に伝統を重んじるだけではなく、和と洋とが心地よく同居する住まい。
さまざまな時代や場所の文化が入り交じる、現代の日本だけが持つ魅力がそこにはある。
〈ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵〉はこの先、長い時間をかけて番町の街並みに新たな歴史を紡いでいくことだろう。
ずっとここに住み続けたいと誰もに思わせる“一生もの”の住まいである。

紛れもない都心の一等地に新たに完成した建物ながら、重厚感のある落ち着いた佇まいで、歴史ある周囲の景色に違和感なく溶け込んでいる。
都心に住むことの醍醐味をすべて叶えてくれる場所。
自然の豊かさ、交通や買い物の便、文化・教育施設の充実――。人が住環境に求めるものはさまざまだが、この辺りは共通するところだろうか。
それらが心ゆくまで満たされることは、人がその場所に根づき、長く住み続けていくための大前提となる。そういう意味では〈ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵〉が立つ東京都千代田区三番町ほどの土地も珍しいのではないか。
都心最大級の緑域でもある皇居のお堀端、江戸時代に築かれた千鳥ヶ淵を目の前にする角地。木々や動物たちが息づく自然の一角とでもいうような場所だ。

そもそも番町界隈は、古くからのお屋敷町。江戸時代には白河藩主の屋敷が置かれたほか、明治から大正、昭和にかけては藤田嗣治や島崎藤村、菊池寛などの芸術家や作家たちも居を構えた。
時代を下って現代は、国立近代美術館や国立劇場、日本武道館など文化施設の多いエリアともなった。長い時間をかけて文化的薫りの高い土壌が培われてきたのだ。
さらにこのエリアは、都心ならではの便利さを享受できる場所でもある。官公庁や世界の企業が集まる大手町、丸の内、永田町はもとより、銀座、赤坂、六本木などショッピングや数々のエンターテインメントが待つ街へも至近。公共交通機関も不足なくそろうから、アクセスはどこであってもスムーズだ。
高層集合住宅の黎明期、1970年から続く「パークハウス」ブランドの哲学を受け継ぐ、「ザ・パークハウス グラン」。
その歴史と実績があってこそ、自然、文化、機能性と、都心居住の醍醐味をすべて手にすることが可能となったのだ。

北の丸公園の緑の中にある科学技術館。科学技術や産業技術の紹介を主軸とした博物館。体験型の展示の多さでも知られ、子どもたちにも人気が高い。

昭和期の日本を代表する建築家のひとり、谷口吉郎設計による東京国立近代美術館。フィルムセンターやアートライブラリーも備えている。

1964年の東京オリンピックの際に、柔道競技場として建設された日本武道館。現在は武道大会はもちろんのこと、数々のイベント会場としても使用される。


武蔵野台地から、かつての日比谷入江へと注ぐ川の流れをせき止めて作られた千鳥ヶ淵。岸辺は自然の地形が残っており、春には満開の桜で埋め尽くされる。
土地の魅力を最大限に引き出した幸せな建築。
設計を手掛けた三菱地所設計の石井邦彦さんと、施工を担った竹中工務店の西居昭彦さんの案内で〈ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵〉の見学をする前田紀貞さん。
設備フロアを覗き込んだり、見過ごしてしまいそうなディテールについて質問を投げかけたりと、建築家ならではの鋭い視線が建物の内外に隈無く向けられた。
同じプロとして、〈ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵〉をどのように捉えたのだろうか。

――見学を終えてみていかがでしたか。
前田紀貞(以下、前田)
いわゆる高級マンションと呼ばれる建物は数々ありますが、実際にそう呼べるだけの空間の質を備えた建物は、とても少ないように思ってきました。でもこの〈ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵〉は、明らかに〝高級〟と呼ぶのにふさわしい空間の質を持っていました。とてもまっとうで、想像以上の出来栄えですね。細かなところまですごくよく吟味され、検証されているのがわかる。どこかツッコミを入れたかったのに、よくできているなあというのが正直な感想です(笑)。
石井邦彦(以下、石井)
“まっとう”と言っていただけるのはとてもうれしいですね。この建築では、土地柄を踏まえた正統派のものを作りたいという気持ちが強かったんです。
前田
軸線を意識して、建物を敷地に対して斜めに振ったり、建物の外形が不定形になったりしたと、石井さんに見学中に聞きました。いくつもの軸線を意識するのは、ともすればデザイン上の制約になりかねないことですが、ここではそれがすごくいい方向に働いていましたね。たとえばエレベーターを降りて住戸へと至る廊下。ただまっすぐなのではなくて、少し折れ曲がっていたりして、奥へ奥へと歩きたくなる。歩いていて楽しい廊下というのは、そう作れるものじゃないですよ。

石井
それは意識していました。廊下にせよ、共用部にせよ、見え隠れするというか、少しずつシーンが変わっていくほうが魅力を感じるんです。
前田
そういう意味では、回遊式庭園のような感じもありますね。歩き回るにつれて、さまざまな場が現れる。その印象が積み重なって、全体の印象を形作っている。とても日本らしい美意識だと思います。
――ロビーから見える、水の流れる中庭では、ずいぶん長い時間見学をされていましたね。
前田
これもまた、建物を敷地に対して斜めに作ったことで生まれた余白を上手に利用した場所。外の景色とはまた異なるシーンが立ち現れて、建物の魅力が一段と深さを増しますね。音楽でいうならば、主旋律が複数存在するポリフォニーのような魅力です。

石井
施工上クリアすべき点も多かったのですが、日本建築で感じられる自然と室内との一体感を作り出したかったんです。周囲の自然の景色ももちろん素晴らしいけれど、滝の流れは一瞬で気分の変わるインパクトがある。
――共用部や住戸のインテリアにはどんな印象を持たれましたか。
前田
眺望のよさはもちろん、この場の大きな魅力。それが存分に生かされていましたね。敷地の条件がいいからといって、その魅力をきちんと引き出して建物を作るのは、実はけっこう難しいことです。バルコニーからの眺めは、森を見下ろす上層階もいいけれど、木々が目の前に来る低層階もまたいい。それぞれの高さでの楽しみが用意されていました。
――素材使いはどうでしょう?
前田
石にせよ木にせよ、とてもいい素材を使っているし、ごく細かなディテールまで全く手を抜いていない。さすが三菱地所さんだなあと。
石井
確かにディテールの作り方などは、社の伝統という側面もあると思います。基本をしっかりおさえていこうという意識はあります。

前田
建築の設計をしていると、デザイン上でやってみたいことがあっても、メンテナンスや安全性の観点から、やらないほうがベターというときがある。建築は、デザインの美しさだけをなぞってはいけない。もっというならば、デザインばかりを優先した建築には魅力がないと思うんです。この〈ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵〉は、表面のデザインを超えた、とても質のいい〝空気〟があると感じました。建築とは床・壁・天井を作るものですが、実際にはそれが囲む空気こそが何より大切なんです。
石井
空間の質ですね。言語化しづらい。でも、そこに思いを馳せることがとても大切だと思っています。
前田
それから、デザインはかっちりとしているのだけど、いい意味での“ボケ味”があるという印象です。たとえばドアの木枠や、バルコニーの庇など、線の重なっているディテール。重なりが陰影を生み、輪郭がにじんでいるような、かすんでいるような印象を受けました。ボケ、にじみ、かすれ。これらはすべて日本独特の感性ですね。
石井
線をずらすことで生まれる陰影のことは強く意識していましたが、そういうふうに言語化することはできませんでした。とても参考になります。
――それらを実現した施工についてはどうでしょう?
前田
本当に細かな作りですから、施工は相当大変だっただろうと思います。設計はもちろんですが、施工も優秀な方々の集まりだったということが、容易に想像できる。僕らが木造2、3階建てを作るくらいの期間で、これだけの規模の建物が、このクォリティで仕上がるんだから!(笑)

西居昭彦
確かに施工者泣かせの難しいディテールの連続でしたが、弊社としても、ほかではあまり使わないようないい素材を贅沢に使っているので、それを生かした作りにしたくなるんです。この現場には、述べ60万時間以上、職人さんの数でいうと述べ約8万人が入りました。その方たちの魂がこもった仕上がりになっていると思います。
石井
設計者、施工者、クライアントが、同じ目線でいいものを目指すことのできる現場でした。チームワークはとてもよかったと思います。
前田
海外で現場を経験するとよくわかるのですが、日本の施工の質の高さは、世界のトップレベル。職人さんの技術が本当に優れています。「日本らしい正統派の建築を」ということをコンセプトに据えたからといって、安易にいわゆる“和”に走ることなく、それが何を意味するのかを咀嚼し、考え方や手法によって表現している。とても幸福な建物ですね。

前田紀貞
建築家。1960年東京都生まれ。京都大学工学部建築学科を卒業後、大成建設設計本部を経て、1990年前田紀貞アトリエ一級建築士事務所を設立。
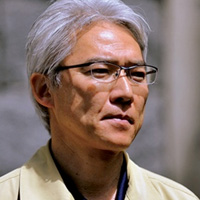
西居昭彦
株式会社竹中工務店 東京本店 作業所長。1964年大阪府生まれ。金沢大学大学院修了後、竹中工務店に入社。2011年〈ザ・パークハウス 六番町〉新築工事作業所長。

石井邦彦
株式会社三菱地所設計 建築設計住環境部 副部長。1967年神奈川県生まれ。1993年東京理科大学大学院修了後、三菱地所に入社。2001年三菱地所設計。
ザ・パークハウス グラン 千鳥ヶ淵(販売済)
●所在地/東京都千代田区三番町2-1(地番)
●構造・規模/鉄筋コンクリート造・鉄骨造、地上14階、地下2階、塔屋1階建
●総戸数/73戸
●竣工/2015年3月
●売主/三菱地所レジデンス(株)
●設計/(株)三菱地所設計、(株)竹中工務店
●施工/(株)竹中工務店
photos by Yasuo Konishi
text by Sawako Akune
edit by Kazumi Yamamoto