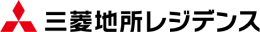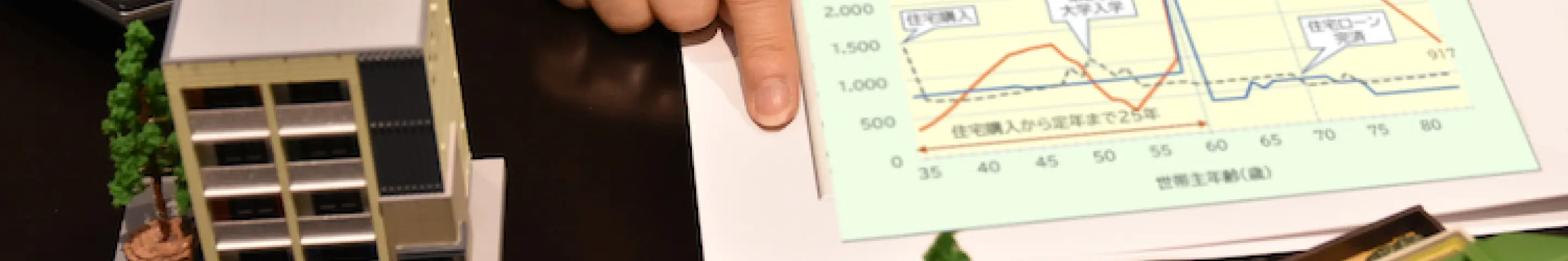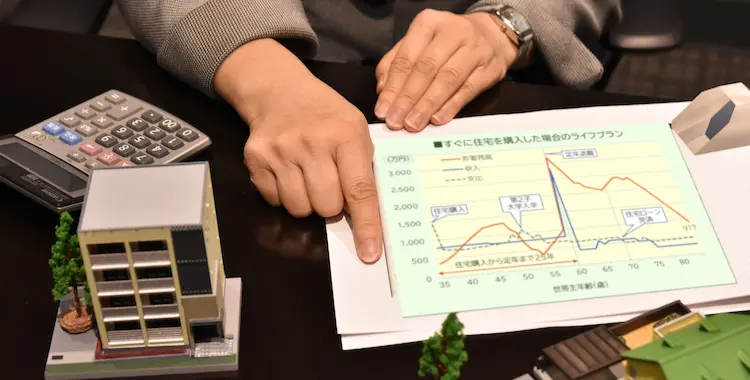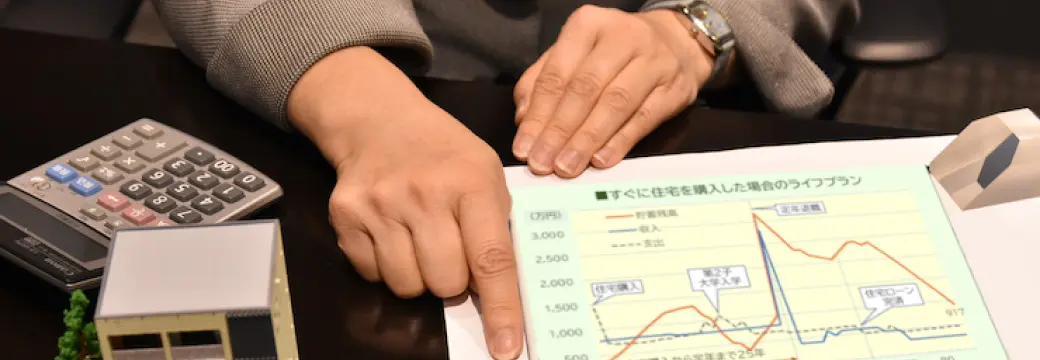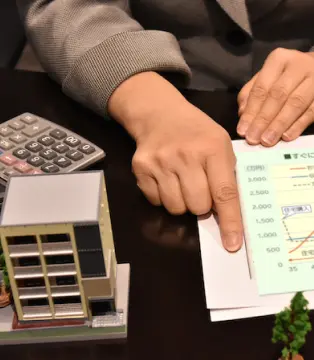三菱地所のレジデンスクラブにログイン
Machi Passユーザの方はこちら
Machi Passユーザではない方はこちら
三菱地所のレジデンスクラブをご利用いただくためには、
三菱地所グループの共通ID「Machi Pass」との連携が必要です。
Machi Pass未連携のアカウントを
お持ちの方はこちら
※「三菱地所のレジデンスクラブ」サイトへ遷移します。
powered by