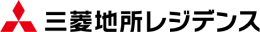ザ・パークハウス ストーリーザ・パークハウス 芦屋
2016年07月27日
兵庫県芦屋市。北に六甲山、南に大阪湾を望み、中央に芦屋川が流れるこの地は、古くから緑豊かで風光明媚な場所として知られています。
なかでも、鎮守の杜・芦屋神社を擁する高台一帯は「芦屋山手」と位置づけられ、芦屋らしい情緒と歴史を感じさせるエリア。
そんな芦屋らしい街並みとの調和をはかりつつ、随所に“ここだけにしかない”こだわりを結集させた邸宅、「ザ・パークハウス 芦屋」をご紹介します。
目指したのは、芦屋山手の景色との一体化

「ザ・パークハウス 芦屋」が建つのは、芦屋神社に隣接し、神社の表参道に沿った場所。芦屋市では、条例によって一定規模以上の敷地面積の確保や緑化を義務づけるなど、町の景観を守るために長年にわたって建築物に厳しい規制がかけられてきました。なかでも芦屋神社周辺は「六甲山風致地区」に含まれ、自然環境の維持が求められるエリアです。そのような地域に新しく建つ集合住宅として、設計担当者が一番に考えたのは、“周辺地区との調和”でした。

歴史ある芦屋神社に隣接することから、土地の風土になじむように和の雰囲気を大切にしたい。また、芦屋山手地区といえば、近代建築の三大巨匠と呼ばれるアメリカの建築家フランク・ロイド・ライトが大正末期に設計した旧山邑家住宅(現在はヨドコウ迎賓館)に代表される、先進的でモダンな洋館のイメージもあります。
日本らしい伝統美を継承しながら、西洋の新しい感覚も受け入れて、育まれてきた芦屋独自の風景。そこにしっくりと溶け込み、さらに“ここだけにしかない邸宅美”をもつ住まいを追求した結果、辿り着いたのは、敷地の中央に枯山水の中庭を設けることでした。そして、住戸は北と南の二棟構成とし、三階建ての低層住宅でありながら1フロア2邸に対して1基のエレベーターを配置することで、邸宅にふさわしいゆったりとした住空間を演出しました。
露地を抜けて、私だけの空間へ

枯山水の中庭を設けることが決まったことで、「日本人の美意識を追究した街並の継承と共創」という全体のコンセプトがより明確になった「ザ・パークハウス 芦屋」。エントランスから住戸までの動線には「露地」のイメージを再現しました。露地は日本庭園の様式の一つでもあり、人を茶室に導き入れる通路という意味合いがあります。阪神間の文化施設である香雪美術館(神戸市東灘区)の茶の湯文化のイメージともつながります。
外の道路から敷地に入り、しなやかに伸びるモウソウチクの林を抜けてエントランス、エントランスホールと進んで階段を降りると、そこにある通路のようなスペースは「下露地」。さらにそこから続く各館の共用廊下は「中露地」。そして、2邸に1基のエレベーターを出て自邸までの空間を「上露地」…という三段階の露地に見立て、それぞれの露地を抜けて行くごとにシーンが切り替わり、外の世界から隔絶されて、よりプライベートな場所へと帰っていくアプローチを演出しました。
また、エントランスからエントランスホールに入っていくと視界が一気に開け、空間が広がっていく感覚は、茶室のにじり口(茶室にある小さな出入り口)にも似ています。
現代的枯山水は、住む人のためだけのランドスケープ

中庭は、ここに住む人だけが楽しむことができる奥庭的な空間です。枯山水とはいえ、ここは芦屋。京都の神社仏閣にあるような純和風の日本庭園のイメージではありません。置き石や敷石、砂利など和のテイストをベースにしながら、新しさを感じさせるデザインを目指しました。その一例が、茶室などに見られる「色紙窓」のエッセンス。大きさの違うふたつの窓を上下にずらして配置する色紙窓のように、植栽の面を前後左右にずらして置くことで、直線的な美しさや奥行き感など、伝統的な枯山水とはひと味違った表情が生まれました。
植栽は、六甲山にあるのと同じ種類のモミジや、市の花であり、芦屋神社に群生するコバノミツバツツジなど、周辺地域に自生する樹木や花を中心にまとめています。
昔ながらの芦屋の自然と調和しつつ、四季折々の彩りを愉しむことができるこの中庭は、住む人ですら中に入ることのできない“眺めるための庭”。「ザ・パークハウス 芦屋」に住む人だけが見ることのできるランドスケープです。
日本の伝統技術が息づく“一点もの”の素材を厳選



庇などの水平ラインと柱などの垂直ラインを強調し、艶やかな質感のある素材を用いるなど、和洋の美しさを漂わせる「ザ・パークハウス 芦屋」の外観デザインは、旧山邑家住宅のイメージとのつながりも意識しています。周囲の景観と融合しながら、“ここだけにしかない邸宅美”を生み出すために、マテリアルは検討を重ねて選定しました。
たとえば壁に用いたタイルは特注品で、一枚一枚、すべてが職人のハンドメイド。特に、エントランスの外壁とラウンジの装飾壁に採用したオリーブグリーンのタイルは釉薬を施して焼いたもので、温かみのある風合いや独特の艶が生まれ、時間や光によって、見る人にさまざまな印象を与えてくれます。

エントランスホールで印象的なのは、一面に広がる光壁。これはガラスの間に創作和紙をはさみ込んだもので、この和紙も手作りの逸品。差し込む光に和紙ならではのやわらかさが加わっています。夜、帰宅したときに外から見えるホールの明かりは、ほっと心を和ませてくれます。一方、ホールの壁と床には光沢のある大理石や御影石を採用し、芦屋らしい洗練された雰囲気を漂わせています。
和の手仕事の技を感じさせる、こだわりの素材の数々。それらを随所に用いて華美にならない落ち着きのある空間を造り上げた「ザ・パークハウス 芦屋」は、芦屋山手で新しい時を刻みながら、住まう方々に、ここだけにしかない上質な暮らしをお届けします。
その他の写真
企画担当からのメッセージ
昔ながらの邸宅が多く、独特の洗練された雰囲気が漂う芦屋の山手。そこにふさわしい邸宅とはどういうものなのだろうか。芦屋神社に隣接する「ザ・パークハウス 芦屋」の開発は、それを考えるところから始まりました。建物の表情を印象づけるマテリアルの選定にはとくにこだわりました。外壁やエントランスの壁などには街並と調和するように温かみのある色彩と質感の材料を用い、ハンドメイドのせっ器質タイルや釉薬を施した特注タイルを使っています。一方、エントランスホールには光沢のある大理石や御影石、さらに創作和紙の光壁を採用して洗練された空間を演出しました。こうして一つひとつ細部にまでこだわった素材が、全体の味わい深い表情を創り上げています。
関西支店としても、芦屋の地にこのような規模の集合住宅をつくるのは初めてで、また、なかなかない機会ですので、設計者とやりとりを重ねながら作り込みをさせていただきました。やりがいも大きく、このような物件をみなさまにお届けすることができて、非常に満足しております。