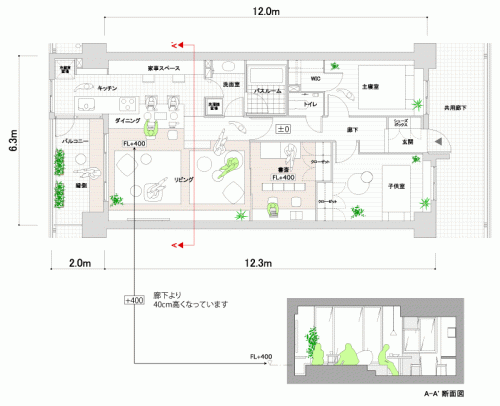-
#118 これからのリノベーションについて vol.2 ~キッチンと洗面化粧台を一緒にしちゃいました!
update:2022/03/22
-
#117 これからのリノベーションについて vol.1 ~クローゼットの使い方を考える
update:2021/09/02
-
A044「玄関収納の使い方・バルコニーでの過ごし方について」のアンケート報告
update:2023/04/03
-
update:2023/03/31
-
update:2016/03/02
-
M28 食器棚について 〜入居者アンケートと訪問調査の中から
update:2015/12/24
-
update:2019/02/06
-
RT015「夫婦二人暮らしのくつろぎ空間」(Plan 17)
update:2018/10/23
-
J006 リノベーションで自由度のあるクローゼットを作りました
update:2022/01/26
-
update:2016/04/27
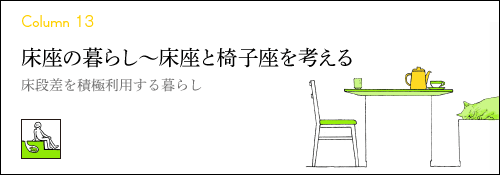
#13 床座の暮らし〜床座と椅子座を考える(床段差を積極利用する暮らし)
以前行った調査では、意外にも多くの人が床座の暮らしをしたいと答えました。
床座の暮らしをしたい 72%(※)
※無印良品の家 みんなで考える住まいのかたち 「部屋の使い方についてのアンケート」より
実施期間:2011年8月23日(火)〜 2011年8月30日(火)
また、テレビを見るときには床でゴロゴロしながら見たい、特にリビングではソファに座るよりも床に座りたいというのは、どうやら多数派のようです。
床座というのは、日本の文化そのものです。それは靴を脱いで暮らすという、日本が誇る清潔な文化だからこそできることと言えるかもしれません。
また座るだけでなく、畳の上で横になるのも気持ちのいいものです。
日本の住宅史を見てみると、一般家庭にキッチンが入り、そしてダイニングでテーブルと椅子での暮らしが始まるのは1950年代の終わりの頃のこと。意外と最近の話です。
椅子の生活で、食事をする場所が固定されました。つまり、それまでちゃぶ台をたたんで寝るという暮らし方から、食べるところと寝るところは分けて暮らすという新しい暮らし方が定着していったのです。しかし椅子に座った生活、椅子座の暮らしは床に座った人と目線が合わなかったり、天井高が低すぎたり感じたりもしました。1950年代の日本の一般的な家の天井高は2m10cmぐらいでした。椅子と床に座るのでは目の高さが40cmぐらい違います。しかし、椅子に座った高さに合わせると床座の暮らしには天井が高すぎるようにも思えます。現在のマンションはこの椅子の生活が中心ですから、天井の高さは床座や立った時に合わせて設計されているので、2m50cmぐらいの高さをとっています。
そこで、床に座る部分と椅子に座る部分の床の高さを変えるというのはどうでしょう。
下の図面をご覧ください。キッチンや廊下は床の高さをそのままにして、床座で暮らす部分やテーブルを掘りごたつのようにして、一段高いところに腰掛けられるようにしてみました。
こうして床の高さを変える事で、床に座っても椅子に座っても視線の高さが同じになります。また床を上げることで、そこに生まれた床下のスペースを収納場所にすることもできるでしょう。決して広くはない現代の住宅において、収納スペースの課題を解決するひとつの有効な方法です。そのほか高くなった床に合わせて、ベランダ側に縁側をつくるのも風情があっていいかもしれません。床の高さが外に伸びることで、部屋も一層広く感じるでしょう。
最近では、欧米でも靴を脱いで室内履きに履き替える家をよく見かけます。靴を脱いで床に座る、この解放感は一度味わうとなかなか忘れることはできません。
いかがでしょうか。床座の暮らしについて、もう一度考えてみませんか?
日本の家は寒い冬でもあたたかくなりましたが、こたつを囲んでの家族の団らんもいいものです。
みなさんのご意見をぜひお寄せください。