-
#118 これからのリノベーションについて vol.2 ~キッチンと洗面化粧台を一緒にしちゃいました!
update:2022/03/22
-
#117 これからのリノベーションについて vol.1 ~クローゼットの使い方を考える
update:2021/09/02
-
A044「玄関収納の使い方・バルコニーでの過ごし方について」のアンケート報告
update:2023/04/03
-
update:2023/03/31
-
update:2016/03/02
-
M28 食器棚について 〜入居者アンケートと訪問調査の中から
update:2015/12/24
-
update:2019/02/06
-
RT015「夫婦二人暮らしのくつろぎ空間」(Plan 17)
update:2018/10/23
-
J006 リノベーションで自由度のあるクローゼットを作りました
update:2022/01/26
-
update:2016/04/27
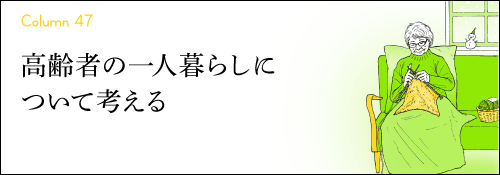
#47 高齢者の一人暮らしについて考える
日本の家族の平均は2.4人、そのうち34%が一人暮らしです。(2010年、総務省国勢調査より)一人暮らしの高齢者が増えている事や、若い世代が結婚しない事などがその理由です。成熟国家の宿命かも知れませんが、その中でも日本の高齢化率は世界一位、2050年には、40%にも達します。元気なうちはいいですが、介護が必要になった時、家族がいない一人暮らしの老人はとても不安な想いをすることでしょう。また人生の最後を病院で過ごす事が多い日本ですが、今後ケアする看護や医師や施設の数はますます足りなくなり、自宅で一人亡くなる方も増えると言われています。
こうしたことを考えると、元気な時から他人ともっと関わる暮らしが必要かもしれません。先日のアンケートでも、元気な間は働きたいという方が多くいました。体が動く時に地域の活動や近隣の人との接点を多くすることを社会の仕組みとして考えられるといいと思います。
考えてみると、日本はもともと地域の活動が盛んな国、良くも悪くもお互いに関心を寄せ合って生きてきた国民でもあります。隣組や、地域が共同で持つ入会地、里山のような仕組みをずっと守ってきました。戦後、急速に高まった都市化はそうした隣人や地域とのつながりより個人の自立した暮らしを優先していくようになってしまったのです。
そうしたことを解決するために、高齢者施設を自分たちの手で運営しているあるオランダの施設パガニーニホフをご紹介します。(オランダ、スパイケニッセ)この施設の入居は55歳から。現在70人ほど入居しています。元気な時は自分より高齢者の、または介護の必要な人の面倒を見ます。その時間に応じてポイントが加算され、自分が誰かのサポートを受けたい時はそのポイントを使って暮らすというのです。興味深い事は、こうした暮らし方でコミュニティーはより活性化されて、かえって楽しい時間を過ごし、元気な時間がのびるというのです。ただ「コミュニティー」と声を大にしても人が自然に集まるわけではありません。そのためにも何か具体的な行動をすること、共同で仕事をすることでコミュニティーは生まれるのだとも思います。
人間はだれしもが老います。そしていつか死にます。元気な間は死ぬという事を積極的には受け止められないのが普通です。
しかし、どうしても「老い」という課題は避けられない事です。特に高齢化の問題が社会問題となっている日本では、一人で暮らすということ、しかも年齢を重ねてからの一人暮らしについて考えざるを得ないとも言えないでしょう。将来の不安を取り除く事で、今の暮らしを安心して楽しむという事も出来るとも言えます。
あらためて、こうした一人暮らしをサポートができるような建築とそれを支える運用の仕組みをつくることが必要に違いありません。
是非みなさんのご意見をお寄せください。

